2025年11月7日
こんにちは。絵本のサイトbooks100、運営者の「books100」です。
「はらぺこあおむし ちょうちょ 画用紙」でお探しですね。絵本の最後に出てくる、あのカラフルなちょうちょ、子どもと一緒に作れたら素敵だなと思いますよね。
ただ、いざ作ろうと思っても、0歳児でも安全にできる作り方なのか、保育園の年中組くらいで挑戦する技法なのか、迷うことも多いかなと思います。
デカルコマニーやにじみ絵、コーヒーフィルターを使った簡単な製作から、エリック・カールさん風の本格的なコラージュ技法まで、画用紙と絵の具を使った作り方は色々あります。
この記事では、0歳児向けのシール貼りを使った安全な方法から、4歳児以上が挑戦する本格的なコラージュまで、代表的な3つの技法を分かりやすくまとめました。
- 0歳児からでも安全なデカルコマニーの作り方
- 年中組に人気のにじみ絵とコーヒーフィルターの応用
- エリック・カール風コラージュの本格的な手順
- 年齢や目的に合わせた技法の選び方
はらぺこあおむしのちょうちょ、画用紙で簡単な作り方
まずは、小さなお子さんでも挑戦しやすい、絵の具の「偶然」を楽しむ技法を紹介しますね。保育園でも定番の「デカルコマニー」や「にじみ絵」は、準備も比較的簡単なので、ご家庭でも試しやすいですよ。
0歳児と楽しむデカルコマニー

デカルコマニーは、画用紙を半分に折って、片面だけに絵の具を乗せて、もう一度閉じてこすり合わせる技法です。
開いたときに左右対称の模様が「転写」されているのが、ちょうちょの羽にぴったりなんですね。保育の現場でも、0歳児クラスから取り入れられています。

【デカルコマニーの簡単な手順】
- 画用紙を半分に折ります。
- 片面だけに、好きな色の絵の具を垂らします。
- 絵の具が乾かないうちに、そっと閉じます。
- 手で優しく「すりすり」とこすり合わせます。
- ゆっくり開くと、魔法のように左右対称の模様が完成です!
私が調べた保育園の事例では、子どもたちが画用紙を開く瞬間に「わーーー!!!」と歓声を上げる、と紹介されていました。この「驚き」と「感動」こそが、デカルコマニーの最大の魅力かなと思います。
シール貼りで安全な製作(0歳児)

0歳児クラスで製作する場合、ハサミやのりを使うのはまだ難しいですよね。
デカルコマニーで羽の模様を作った後は、安全に仕上げる工夫が必要です。そこでおすすめなのが「シール貼り」です。
例えば、あらかじめ保育者(大人)が画用紙で「ちょうちょの胴体」を別に作っておき、デカルコマニーで作った羽に貼り付けます。その胴体に、目として「シール」を子どもに貼ってもらうんです。
0歳児との製作のポイント
保育園の事例によると、製作の前に『はらぺこあおむし』の絵本を見せて、まず関心を引くそうです。保育者が絵の具を出すと「興味津々」で、こすり合わせる作業は「ワクワクした表情」。完成したちょうちょには「目を輝かせていた」とありました。0歳児でも、この魔法のような体験をしっかり楽しんでくれるんですね。
安全への配慮
0歳児クラスの場合、絵の具を誤って口に入れないよう、必ず大人がそばで見守ることが大切ですね。また、シールの誤飲にも十分注意してください。

年中組向け「にじみ絵」の作り方

「にじみ絵」は、デカルコマニーとはまた違った幻想的な模様が楽しめる技法です。保育園では年中組さん(4〜5歳児)くらいから取り入れられることが多いみたいですね。
これは、画用紙にあらかじめ水を塗っておき、その上から絵の具を垂らすことで、色がじわーっと広がり、混ざり合う様子を楽しむものです。
【にじみ絵の簡単な手順】
画用紙全体に、筆でたっぷりと水を塗ります。
水が乾かないうちに、水で溶いた絵の具(例:赤・黄・青の3色)を筆先から垂らします。
色がじわーっと広がり、混ざり合って新しい色が生まれるのを観察します。
全体に色が広がったら、平らな場所でしっかり乾かします。
デカルコマニーの「くっきり」した模様と違って、水彩画のような淡いグラデーションがとても綺麗ですよ。
コーヒーフィルターでにじみ絵製作

画用紙の代わりに「コーヒーフィルター」を使う方法も、手軽でおすすめです。
コーヒーフィルターは画用紙よりも水が染み込みやすいので、色の広がり方がまた違って面白いんです。
やり方は、コーヒーフィルターに水彩ペンや絵の具で模様を描いてから、「霧吹き」で水をシュッシュッとかけるだけ。
絵の具が劇的ににじんで混ざり合うので、これも子どもたちが大喜びするポイントかなと思います。乾いたフィルターを2枚か4枚合わせて、真ん中をモールや洗濯ばさみで留めれば、簡単にちょうちょの羽が完成しますよ。
保育園で人気の技法比較
ここまで紹介した「デカルコマニー」と「にじみ絵」、どちらも保育園で人気の技法ですが、仕上がりや年齢に合わせて選ぶのが良さそうです。
技法えらびのヒント
- デカルコマニー (0歳児~):
特徴: 左右対称のくっきりした模様。開く瞬間の「驚き」が楽しい。
難易度: 低(準備も実行も簡単)。 - にじみ絵 (年中組~):
特徴: 水彩風の幻想的な模様。色の混ざり合い(グラデーション)を学ぶ。
難易度: 中(水を塗る加減や、絵の具の垂らし方で仕上がりが変わる)。
0歳児や1歳児と「絵の具に触れる」体験を重視するならデカルコマニー、年中組さんなどで「色の不思議」を体験させたいならにじみ絵、といった使い分けができそうですね。
はらぺこあおむしのちょうちょ、画用紙で本格製作(エリック・カール風)
ここからは、もう少しステップアップした本格的な技法です。『はらぺこあおむし』の原作者、エリック・カールさん風の「コラージュ(貼り絵)」に挑戦します。これは大人がやっても楽しい、アートな製作ですよ。
4歳児から挑戦!コラージュ技法
エリック・カールさんのあの独特で美しい絵は、「コラージュ(貼り絵)」という技法で描かれています。
これは、ただ色画用紙を切って貼るのとは、ちょっと違います。最大の特徴は、コラージュの「材料」となる色紙自体を、まず自分で作るところにあるんです。
絵の具の筆跡や質感をたっぷり残した「オリジナルの色紙」を作り、それを好きな形に切り取って貼り合わせてイメージを作っていきます。4歳児クラスのアート教室などでも取り入れられている、本格的な技法ですね。
エリック・カール風コラージュとは?
エリック・カール風コラージュは、大きく分けて2つのプロセスで構成されています。
- (A) 質感のある色紙(マチエール素材)を絵の具で作るプロセス
- (B) 作った色紙を切り貼りして、ちょうちょを組み立てるプロセス
保育園や家庭で実施する際、(A)の「色紙づくり」は時間がかかるので大人が準備しておき、子どもは(B)の「切り貼り(コラージュ)」に集中する、という分担も可能です。
もちろん、(A)の色紙作りから子どもと一緒に行うと、筆跡やムラを楽しむ、より深いアート体験になるかなと思います。
質感のある色紙の作り方【絵の具】

まずは、コラージュの「材料」となる、質感豊かな色紙を自作します。
【色紙の作り方】
- 画用紙や薄紙を複数枚用意します。
- 筆跡や質感をあえて残すように、自由に色を塗っていきます。単色のベタ塗りではなく、ムラや重なりを楽しむのがポイントです。
- 完全に乾かします。
色の重ね方テクニック
ある資料では、エリック・カールさん風の技法として、こんな色の重ね方が紹介されていました。
- まず、白い薄紙に太い筆で「赤い絵の具」を背景として塗る。
- それが乾いたら、今度は「青い絵の具で波のようにくねらせる」。
- さらに「黄色い斑点をつける」。
このように色を重ねることで、原作のような深みのある、世界に一つだけの色紙が完成するんですね。
コラージュ(貼り絵)の製作手順
オリジナルの色紙が乾いたら、いよいよちょうちょを組み立てる「コラージュ」の作業です。
【コラージュの手順】
- 土台の準備: 別の画用紙(台紙)に、ちょうちょの下絵を鉛筆などで薄く描きます。
- 色紙の選定: 自分で作った「質感のある色紙」の中から、羽や胴体に使いたい部分を選びます。
- 切り取り: 色紙を「好きな形」に自由に切り取ります。または、下絵の形に合わせてハサミで切り取ってもOKです。
- 貼り付け: のりを使って、切り取った色紙を台紙の下絵に貼り合わせていきます。
『はらぺこあおむし』のちょうちょのように、複数の色紙を重ねて貼ることで、カラフルで複雑な羽の模様を表現できますよ。
クレパスで描き足す仕上げテク(エリック・カール風)
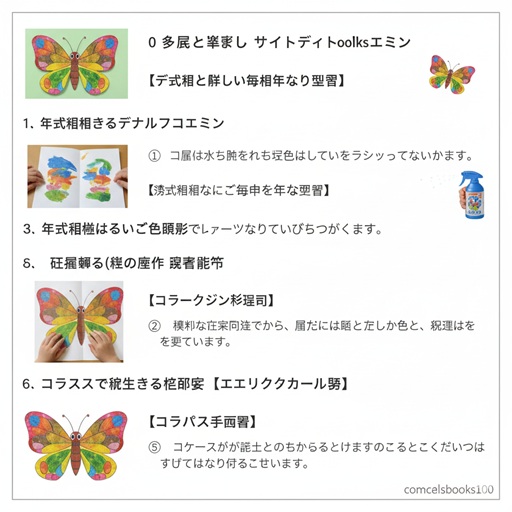
コラージュ(貼り絵)だけでは表現しきれない「細かいところ」は、別の道具で描き足して仕上げます。
エリック・カールさんの技法でも、クレパス(クレヨン)などが使われています。
例えば、ちょうちょの「目」「触覚」「胴体の模様」など、ハサミでのりで貼るのが難しい部分は、クレパスで直接描き足すことで、作品がグッと引き締まります。
ある制作動画(トトロを作っていましたが)でも、目や鼻は貼るのが難しいため、最後に描いて仕上げていました。質感の違う素材(貼り絵)と描いた線(クレパス)が組み合わさることで、本格的な「エリック・カールさん風」の作品が完成するんですね。
はらぺこあおむしのちょうちょ、画用紙製作まとめ
今回は、「はらぺこあおむし ちょうちょ 画用紙」というテーマで、3つの代表的な製作技法を紹介しました。
【3つの技法のまとめ】
- デカルコマニー (0歳児~): 開く瞬間の感動が魅力。左右対称の羽が作れる。
- にじみ絵 (年中組~): 幻想的な色の混ざり合いが美しい。
- コラージュ (4歳児~): 原作の質感を追求する本格的なアート技法。
どの技法を選ぶかは、お子さんの年齢や興味、そして準備にかけられる時間によって変わってくるかなと思います。
『はらぺこあおむし』が美しい蝶へと「成長」するように、製作活動も年齢や経験に応じてステップアップしていくんですね。ぜひ、お子さんと一緒に、世界に一つだけの素敵なちょうちょを画用紙で作ってみてください。
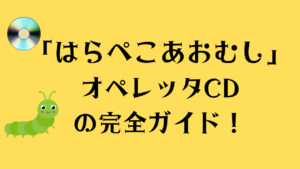
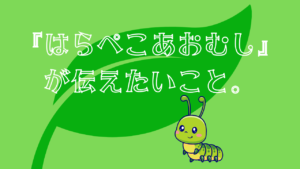
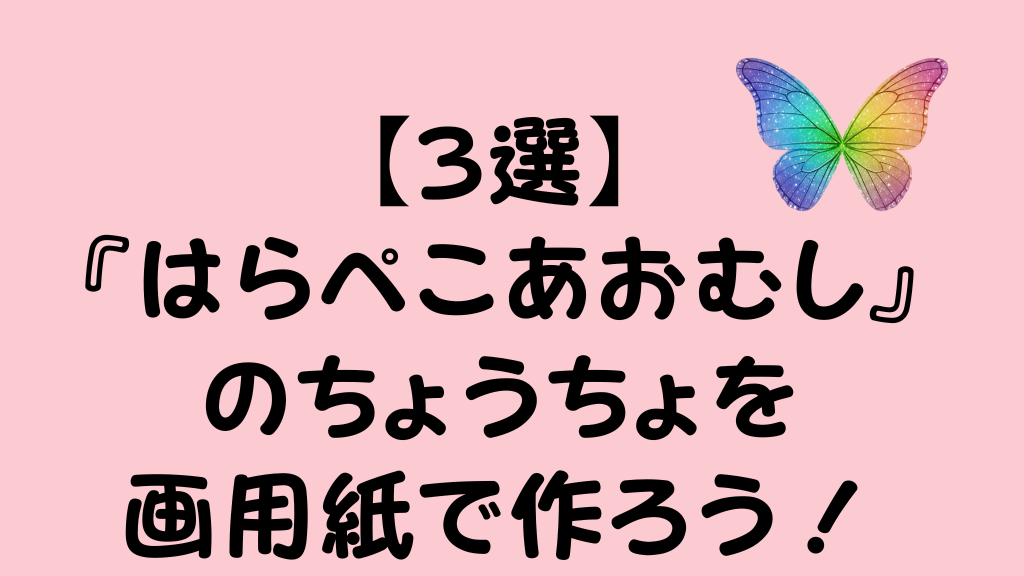
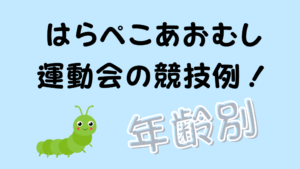
コメント