こんにちは。絵本のサイトbooks100、編集長のbooks100です。
「はらぺこあおむし」をテーマにした運動会の競技について、アイディアを探していませんか。世界中で愛されるあの絵本が、運動会で素晴らしいテーマになるんですよね。
ただ、実際に「はらぺこあおむしの運動会で、どんな競技ができるの?」「うちの子の年齢(0歳や1歳、2歳)でも参加できる親子競技はあるかな?」「3歳児向けの障害物競走や、4歳、5歳が盛り上がるダンスのアイディアが知りたい」「玉入れや衣装、トンネルなどの製作はどうしよう?」といった、具体的な悩みも出てくるかと思います。
また、当日のBGMや著作権について気になる方もいるかもしれませんね。この記事では、年齢別の競技アイディアから運営のヒントまで、幅広くまとめてみました。
- 年齢別の競技アイディア(0歳〜5歳)
- 親子で楽しめる競技の具体例
- 衣装や小道具の簡単な製作方法
- BGM選定と著作権の注意点
はらぺこあおむしの運動会競技、年齢別アイディア
『はらぺこあおむし』が運動会で人気の理由は、「成長」というテーマが運動会とぴったり合うからだと思います。ここでは、子どもの発達段階に合わせた、0歳から5歳までの年齢別競技アイディアを紹介しますね。
0歳・1歳・2歳の親子競技

0歳、1歳、2歳といった乳児クラスの競技で一番大切なのは、保護者の方とのふれあいと安心感かなと思います。運動会といういつもと違う雰囲気に、びっくりしてしまう子もいますからね。
「はらぺこあおむしの大冒険」と題して、親子で楽しめる競技がおすすめです。例えば、こんな流れはいかがでしょうか。
- スタート(ふれあい遊び): 保護者の方がマットに寝転んで「大きな葉っぱ」になります。その上をあおむし(子ども)がハイハイしたり、くすぐり遊びをしたりして、リラックスしてから出発します。
- トンネル探検: 保育で使っているカラフルなトンネルを設置します。あおむしが「食べ物(穴)」をくぐるイメージですね。保護者の方は出口で名前を呼んであげると、子どもも安心して進めます。
- 丘(巧技台)越え: マットで作った低い山(巧技台)を、保護者の方と一緒に「よいしょ」と登って越えます。
- ゴール(果物ゲット): ゴール地点で保護者の方が持つ「果物」のパネルを受け取ってゴールです。
勝敗よりも、「親子で一緒に挑戦できた」「かわいい姿が見られた」というポジティブな体験を共有することが、この年齢の競技の素敵な「ねらい」ですよね。
3歳児向けの障害物競走

3歳児くらいになると、「ごっこ遊び」が大好きになり、想像力が豊かになりますよね。まさに「あおむしになりきる」楽しさを存分に味わえる障害物競走がぴったりです。
「順番を待つ」「合図でスタートする」といった簡単なルールを体験する良い機会にもなります。
アイディア例:あおむし、食べ物をどうぞ!
- スタート: 葉っぱの上の「たまご」(ボール)を1つ拾います。
- マットの山: ハイハイで乗り越えます。
- 一本橋: 低い平均台や床のラインを渡ります。
- 食べ物トンネル: ここが一番の見せどころです。りんごや梨など、絵本に出てくる食べ物の形に切った段ボール(穴あき)をトンネルのように吊るし、そこをくぐり抜けます。
- ゴール: 待っている保護者の方に「たまご」を渡してゴールです。
子どもたちが主人公になりきって、物語の世界に入り込めるようなコース設定が喜ばれると思います。
4歳・5歳で盛り上がるダンス

4歳児、5歳児になると、体も大きく動かせるようになり、クラス全体で協力して何かを表現することに喜びを感じるようになります。運動会のフィナーレを飾るダンスは、まさに圧巻ですよね。
『はらぺこあおむし』のテーマなら、「いもむし」から「蝶」への変身をダンスで表現するのがおすすめです。
ダンス構成案:「ぼくらは蝶になる!」
- 導入(いもむし): 緑色のポンポンなどを持って、小さくうずくまった状態からスタート。ハイハイしたり、体をくねらせたりする動き。
- 展開(食べる): 元気に立ち上がり、手をパクパクさせる動き。「月曜(ジャンプ1回)」など、食べ物の数に合わせた動きも面白いかも。
- 静寂(さなぎ): 曲調がゆっくりになり、再びうずくまって眠る動き。ここで一度ピタッと静止すると、メリハリが出ます。
- クライマックス(蝶): 曲が一番盛り上がる部分で一斉に立ち上がります!背中に隠していた「蝶の羽」(製作物)を広げ、グラウンド全体を自由に飛び回るように踊ります。
この「さなぎ」から「蝶」になる瞬間の演出は、子どもたちの達成感も、見ている保護者の方の感動も最高潮になると思います。
玉入れであおむしが満腹に

運動会の定番「玉入れ」も、『はらぺこあおむし』仕様にすると、ぐっと世界観が出ますよ。
テーマは「あおむしに美味しい食べ物を食べさせてあげよう!」です。
- カゴの装飾: 玉入れのカゴ(ゴール)自体を「あおむし」の顔に見立てます。画用紙で大きな目と触覚をつけ、カゴの入り口を「大きなお口」にします。カゴの後ろに緑色の布で胴体を長くつなげても可愛いですね。
- 玉(ボール)の装飾: 玉を「食べ物」に見立てます。赤(りんご)、黄色(なし)、紫(プラム)など、カラフルなボールを準備します。
「おなかがぺこぺこのあおむし君に、美味しい果物をたくさん食べさせてあげよう!」というアナウンスで始めると、子どもたちのやる気もアップしそうです。
年齢ごとの競技のねらい解説

『はらぺこあおむし』の競技は、単に「楽しい」だけではなく、子どもの発達段階に応じた大切な「ねらい」が隠されています。
| 年齢 | 主なねらい(目的) |
|---|---|
| 0〜2歳児(乳児) | 保護者との愛着形成。安心できる環境での基本的な運動機能(ハイハイ、登る)の発揮。 |
| 3歳児(幼児・低) | 物語の「なりきり」を楽しむ。簡単なルールを理解し、集団での活動に参加する意欲を育てる。 |
| 4〜5歳児(幼児・高) | チームで目標を共有し、協力・競争する楽しさを経験する。ダイナミックな動きで「成長(変身)」を表現し、一体感を得る。 |
このように、年齢に合わせた「ねらい」を意識して競技を設計することで、子どもたちの「できた!」という達成感や、園生活を通した成長の姿を、保護者の方にしっかりと伝えることができるんですね。
はらぺこあおむしの運動会競技を彩る製作と運営
競技アイディアが決まったら、次はそれを実現するための準備ですね。世界観をぐっと高める「製作物(衣装や小道具)」と、意外と見落としがちな「BGMと著作権」について、ポイントをまとめました。
簡単な衣装と小道具の製作

『はらぺこあおむし』の運動会は、視覚的なインパクトも大切です。でも、準備はなるべく簡単にしたいですよね。低コストで雰囲気の出る製作アイディアを紹介します。
最重要アイテム:あおむし帽子
これさえあれば、誰でもあおむしに変身できます。
- 材料: 緑色の画用紙、赤い画用紙(顔)、黄色い画用紙(目)、モール(触覚)、輪ゴム
- 作り方: 緑の画用紙を帯状にして輪っかにします。前に赤い顔と目を貼り、上にモールで触覚をつければ完成。アゴ紐ゴムをつけると安心です。
あおむしの胴体(ベスト)
緑色のフェルトや不織布を長方形に切り、真ん中に頭を通す穴を開けるだけの簡易ポンチョ型が一番簡単です。黄緑色のフェルトで斑点模様をつけても可愛いですね。
トンネルや蝶はどう作る?

競技のキーアイテムとなる「トンネル」と、フィナーレを飾る「蝶の羽」のアイディアです。
食べ物トンネル(障害物)
障害物競走で使う「食べ物」は、大きな段ボールを「りんご」や「なし」の形に切り抜き、中央に子どもが通れる「穴」を開けるのがおすすめです。これをいくつか並べてトンネルのようにします。
補足:トンネル本体
もしハイハイ用の長いトンネルが必要なら、市販のカラフルな「プレイ・トンネル」を購入するのが安全で見栄えも良いかなと思います。もちろん、段ボール箱をたくさんつなげて作るのも楽しいですね。
フィナーレ用:蝶の羽
ダンスのクライマックスで使う「蝶の羽」は、大きめのカラフルな不織布で作るのが軽くて安全です。左右対称の羽の形にカットし、両端に腕を通すゴム紐をつけます。ダンスの途中まで背中に丸めて隠しておき、さなぎから蝶になる瞬間に一斉に広げる演出が感動的です!
BGMにおすすめの音楽と著作権

世界観を作るのに欠かせないBGM。定番はやはり『はらぺこあおむしのうた』ですよね。ダンスにも競技中にも最適です。
でも、市販のCDを運動会で流すとき、「著作権(JASRAC)って大丈夫?」と心配になる先生や保護者の方もいるかもしれません。
著作権のポイント(JASRAC)
結論から言うと、通常の園の運動会であれば、手続きや使用料の支払いは不要なケースがほとんどです。
JASRACの管理上、以下の3つの条件を「すべて」を満たしていれば、原則として許諾手続きは不要とされています。
- 非営利であること(園の運動会はこれに該当)
- 無料であること(観客から料金を徴収しない)
- 無報酬であること(実演家に出演料などを支払わない)
障害物競走のコースアイディア

障害物競走は、まさに『はらぺこあおむし』の物語を丸ごと体験できる花形競技です。年齢に合わせて難易度を変えながら、ストーリーの再現を目指してみましょう。
コース設計例:物語の完全再現
- スタート(誕生): 葉っぱの上の「たまご」(ボール)を拾う。
- 障害1(移動): 「いもむしハイハイ」ゾーン。マットの山や平均台を越える。
- 障害2(食べる): 「食べ物トンネル」。穴の空いた食べ物パネルをくぐる。
- 障害3(さなぎ): 「さなぎマット」。体操マットの上で前転、またはゴロゴロと横転する。
- ゴール(羽化): 先生や保護者が持つ「蝶の羽」のアーチをくぐってゴール!
このように、一つひとつの障害に物語の意味を持たせることで、子どもたちのモチベーションもぐっと上がりますね。
はらぺこあおむしの運動会競技で成長を伝えよう

ここまで、『はらぺこあおむし』をテーマにした運動会の競技アイディアや製作について見てきました。
このテーマがなぜこんなにも運動会で愛されるのか。それは、「小さないもむし」が「美しい蝶」になるという物語が、そのまま「子どもの成長」というテーマと完全に一致するからだと私は思います。
入園・進級したころは小さなたまごのようだった子どもたちが、園生活を通して心身ともに大きく成長した姿。その姿を「あおむしが蝶になる」という物語に重ねて表現できるのが、このテーマの最大の魅力ではないでしょうか。
はらぺこあおむしの運動会競技は、子どもたちにとっても、見守る保護者の方々にとっても、その「成長」を実感できる、思い出深い一日を作るきっかけになるはずです。ぜひ、素敵なアイディアを取り入れてみてくださいね。
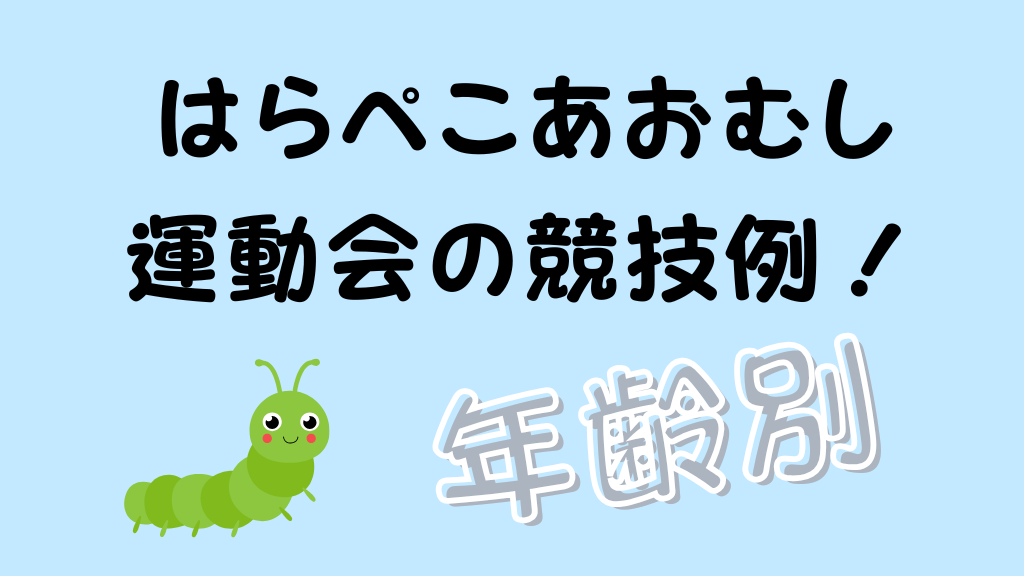

コメント